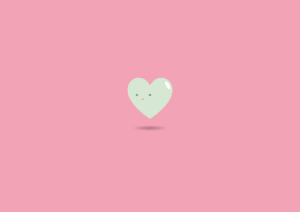「それが本当に“ない”って、どうやって証明するの?」
そんなふうに言われて困ったことはありませんか?
このような“存在しないこと”を証明しようとするのが、「悪魔の証明」と呼ばれる考え方です。
この記事では、悪魔の証明とは何か、なぜ問題なのか、そしてどんなふうに向き合えばいいのかを、わかりやすく解説します。
「やっていない」を証明!?悪魔の証明とはどんな意味?
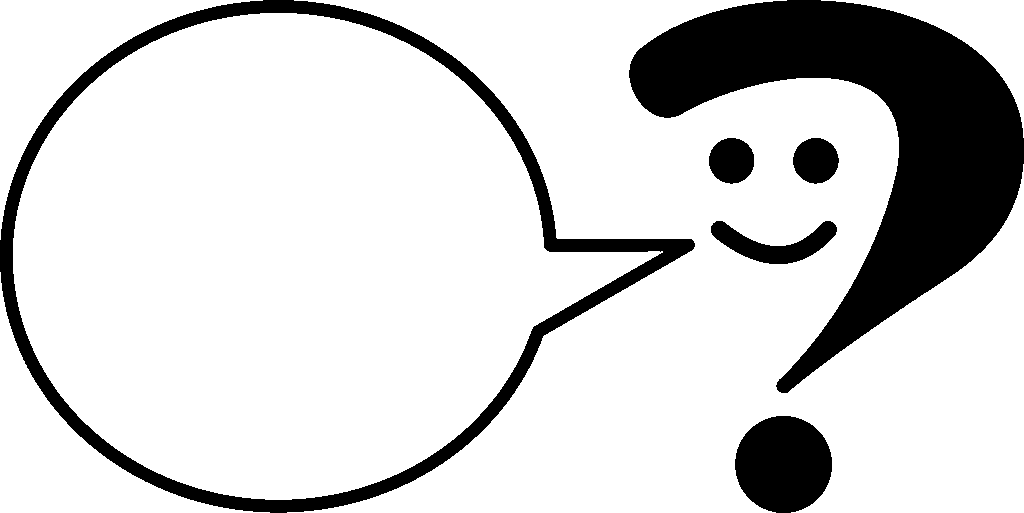
悪魔の証明の定義|裁判ではどうなる?
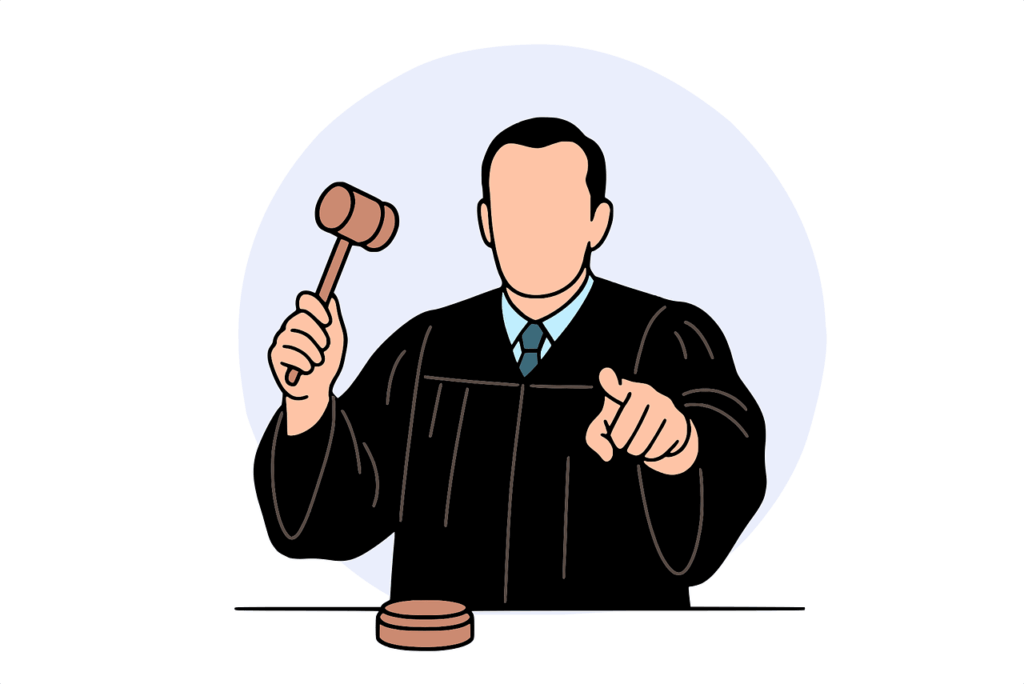
「悪魔の証明」とは、“やっていないこと・ないものを証明しろ!”という無理難題を問う表現のことを言います。
やったこと、あることを証明するのはいくつもの証拠や根拠を提示すれば良いので簡単です。
しかし、やっていないこと・ないもの(消極的事実)を証明するのは、「ないものはない」としか言えず不可能に近いことなのです。
そのため、証明や議論に困難なことから、裁判ではしばしば問題となることがあります。
例えば、「犯罪現場にいたこと」は、防犯カメラや証拠物品、目撃者(嘘をつかないという前提で)によって証明できます。
しかし無罪を主張するには、確実な証拠が不十分である場合が多いため、”疑わしきは罰さず”ということで「推定無罪の原則」が採用されるのです。
悪魔の証明とはなぜこんなにも困難なのか

「証拠がある=やった」となりますが、「証拠がない=やっていない」とはならないのが、悪魔の証明の難しさです。
なぜなら、証拠がないのは証拠が“残されていない”、あるいは“まだ見つかっていないだけ”かもしれないから。
つまり、思いつく限りのあらゆる可能性を潰したとしても、「これ」という決定打がないため、完全にそうとは言い切れずお手上げ状態となってしまうのです。
これを利用して、「ないことが証明できないなら、つまりあったということだ」という安易な結論に持っていきたがる人もいるため、しばしば問題視されます。
「ないことが証明できない=ある」ではなく、「ないことが証明できない=まだ分からない」が通常の答えです。
悪魔の証明の背景
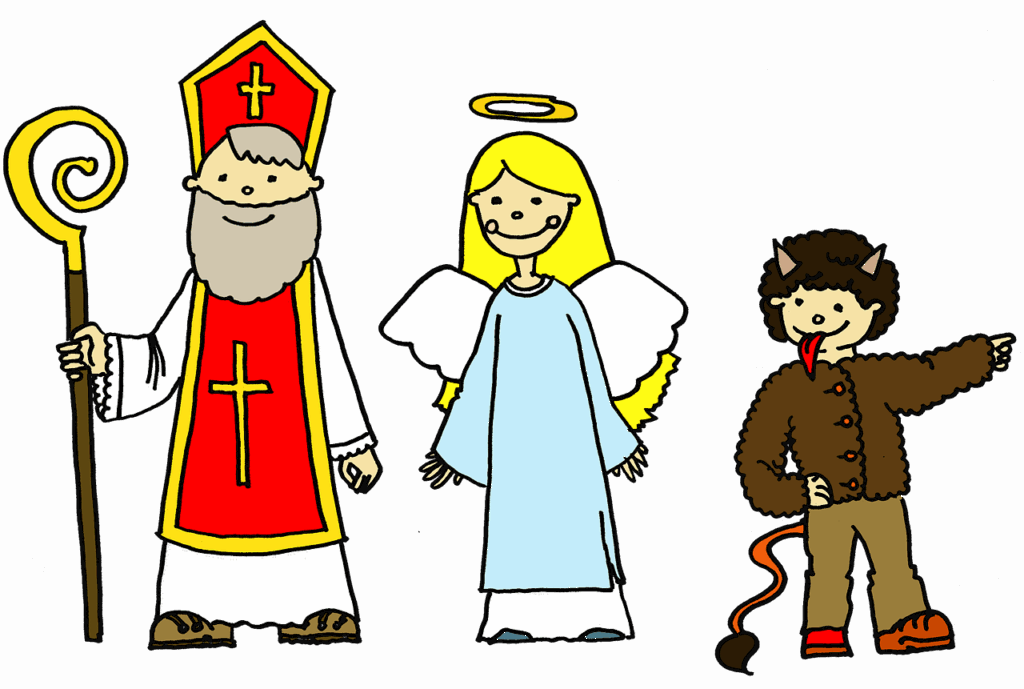
悪魔の証明は、もともと中世ヨーロッパ・ローマ法の下で、法学者たちが「土地や物品の所有権が誰に帰属するのか、過去に遡って証明する」ことの困難さを、比喩的に表現したのが由来です。
土地の所有権を持つ者が、無限に連鎖していく継承取得のいきさつを証明することは、極めて困難であり裁判では必ず負けるだろう、ということを意味しています。
たしかに、「この人の前はその人で、その前はあの人で…」と、その土地の原点を過去数十年、数百年と遡るのは途方もなく、現実的に考えて無理がありますね。
現在では、さまざまな制度や理論の発達により、ローマ法で「悪魔の証明をせよ」という事態は起きていません。
ちなみに、なぜ「悪魔」なのか、に関しては諸説あるので、明確な根拠は見つかっていません。
それなら天使でも宇宙人でも幽霊でも良いような気はしますが…。
しかしイメージや語呂を考えると、やはり「悪魔」がしっくりきますね。
「悪魔の証明」の意味と使い方を例題で分かりやすく解説

分かりやすい例題と使い方
【例① 痴漢冤罪】
👩「今この人に触られた!」
👨「いや、触っていませんよ」
👩「私の後ろにいたじゃない!あなたしかありえない!証明できるの!?」
👨「カメラがないのにどうやってやっていないことを証明するんですか…悪魔の証明ですか?」
⇒カメラがない場合、他の犯人を捜し出さない限り(これも極めて困難)難しい。そもそもこの女性が本当に触られたかも不明。虚言or鞄などが当たった可能性も0ではないため。
しかしこの置換冤罪に関しては、「推定無罪の原則」が適用されることが少なく、やっていないのに仕方なく認めて、示談で済まされてしまうことが多いのが現実だそうです…。
【例② 宇宙人】
👦「宇宙人ていると思う?」
👧「うーん…いないと思うな」
👦「何で?絶対いるよ!いないと思うなら証明してよ!」
👧「いないのにどうやって…悪魔の証明をしろってこと?」
⇒「宇宙人」というものの概念を共通理解したうえで、地球上、宇宙上、思いつく限りすべての場所を探し尽くすことは不可能に近い。さらに、自分が探したときにいなかった場所でも、今後もしくは以前にその場に現れる(現れていた)可能性がある。常時この世のすべてを把握することはできないため非常に困難。
【例③ カンニング】
👨「カンニングしたな!」
👦「してません」
👨「前の人の答案を見ていただろ!やっていない証拠があるなら見せてみろ!」
👦「そんなの悪魔の証明ですよ…」
⇒その生徒の目線と目線の先を完璧に把握できない限りは不可能である。反対に、答えが全く同じだったとしても、この生徒が前の人の答案をカンニングしたと証明するのもまた、困難である。
ドラマ『99.9-刑事専門弁護士-season2』で「悪魔の証明」がテーマに!?
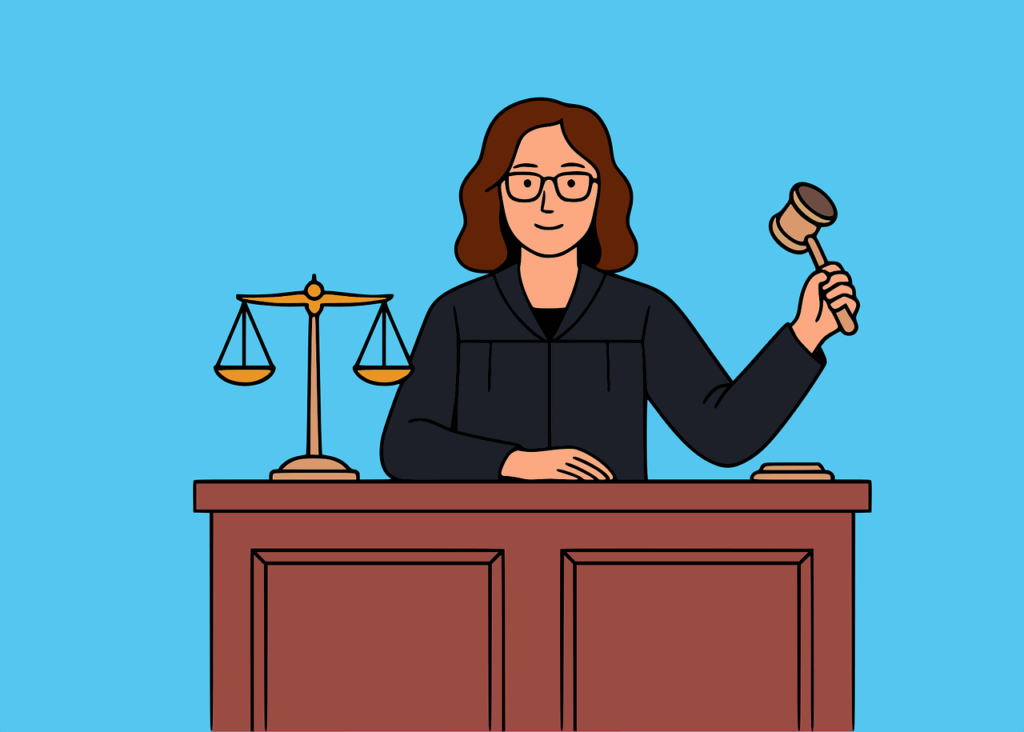
「悪魔の証明」は、2018年に放送された、松本潤主演のドラマ『99.9-刑事専門弁護士-season2』の最終回で登場しました。
ここからはネタバレになるため、これから見てみたいという方は飛ばしてください。
※大体で説明しますので、多少誤りがあるかもしれません。
松潤演じる弁護士のもとに、口論の末に妻を殴って殺害し、それを隠蔽するために自宅兼経営しているそば屋に放火した罪で、死刑囚となっている父親の息子と、その祖母が弁護依頼に来ます。
その父親は、妻との口論を認めたものの、殴ったことも放火もしていないと無罪を主張をしていますが、以下のことが証拠とされ死刑判決が下されています。
・自白すれば息子に会える(無実は裁判でどうにかなる)と言われたので、息子に無実だと伝えるために「やった」と言ってしまった
・事件当日の21:30(妻を殴ったとされた後)に灯油を15リットル買ったというガソリンスタンドの記録と、同時刻に防犯カメラに映った父親の姿がある
・事件後に父親の車から5リットルの灯油が発見されたため、放火に10リットル使ったとされた
しかし父親は、母親と口論後に頭を冷やすために出かけ、手ぶらではなんだからと灯油は買ったものの、5リットルしか購入していないと主張。
検証の結果、時系列は間違っていませんでしたが、松潤は灯油を10リットルきっちり使用する困難さと、灯油は元から5リットルしか入っていなかったと指摘します。
そしてその後、15リットルの購入記録がある時刻(21:30)に、父親が映っていたというガソリンスタンドの防犯カメラの時計が、8分遅れていたことを発見しました。
つまり、15リットルを買ったのは父親ではない別人物だということ、そして父親は21:08分に5リットルの灯油を買ったこと(記録もあり)が判明しました。
ついに放火の無罪を主張できたかと思いきや、なんと検察のヘンテコな反論により裁判官から言われたのが…
「ポリタンクの灯油が1滴も減っていないこと(もともと買った5リットルきっかりが車から発見されたこと)を証明してください」
です!
この無理難題こそが、“悪魔の証明”。
検察の反論などを端折っているので少々分かりづらいかもしれませんが、1滴も減っていないこと=ないことの証明なんて不可能ですし、そもそもそれを裁判で求めるなんて卑劣極まりないですね。
結果的に真犯人を見つけることができたので裁判には勝ちましたが、結局「ポリタンクの灯油が1滴も減っていないこと」なんて証明できませんでした。(というより無理なので、別方向から攻めたということです)
「悪魔の証明」と「ヘンペルのカラス」との関係

「悪魔の証明」の例として、「ヘンペルのカラス」というものが挙げられることがあります。
「ヘンペルのカラス」は、「全てのカラスは黒い」という命題を証明する対偶論法で、「カラスのパラドックス」とも言われます。
対偶論法では、「AはBである」という命題の真偽と、「BでないものはAではない」という真偽は必ず同じになります。
つまり、「全てのカラス=黒」を証明するには、その対偶である「全ての黒くないものはカラスではない」と証明することで解決できます。
しかし逆に言えばこの命題は、この世の黒くないものを全て調べ尽くして、それらの中にたったの一羽もカラスがいないことをチェックしなければなりません。
これは非常に困難なことで、「悪魔の証明」とされます。
ちなみにこの「全てのカラスは黒い」という命題は、アルビノや白変種といった白いカラスが発見されたことで反証されています。
「悪魔の証明」を論破!求められた時の対応方法とは?
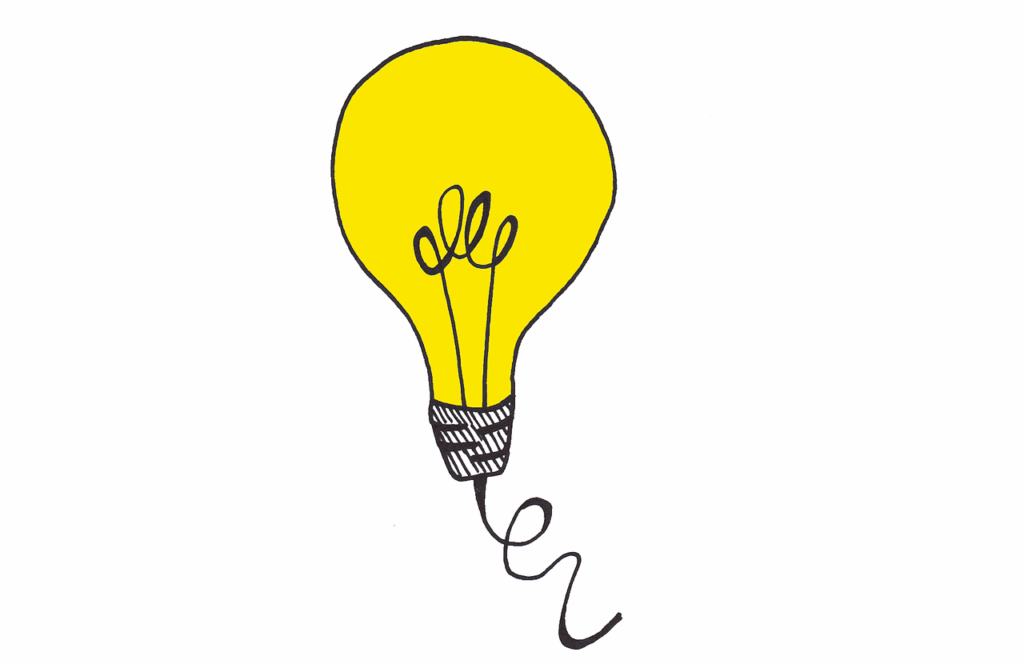
日常生活でも、意図してか否か「悪魔の証明」を求めてくる人がいますが、対応方法が分かっていないと論破されてしまいがちです。
しかし「悪魔の証明」は、本来証明してほしい(「証明しろ」と主張する)側が自分でどうにか(証明)することが基本です。
あくまで答えを知りたいのは「証明しろ」と言ってきた人であって、(勝手に)主張をしてなおかつ相手に「ないものを証明しろ」というのは、あまりにもフェアではありません。
「悪魔の証明」を求めるのは、自分が「ある」ことを証明できないため、相手に証明責任を押し付けて責任転嫁しているのです。
たとえば、「冷蔵庫にあった私のプリン食べたでしょう!」と、まあマンガやアニメでよく聞くようなセリフを言われたとします。
もちろんあなたは食べていないので「食べてない」と返しますが、「じゃあ証拠はあるの?」と言われたら、食べてないものは食べていないので、証拠などありません。
そんな時は「私が食べたと言う証拠はあるの?」と、まずは主張してきた相手がその証拠を提示するよう求めてください。
それがルールというものです!
真に受けて焦ることなく、「それって、あなたが証明することじゃない?」と冷静に対応し、逆に相手を論破しましょう。
まとめ
「悪魔の証明」とは、“存在しないこと”を証明する難しさを表した言葉で、時に見えない圧力やずるい議論の手段として使われることがあります。
本来、何かを主張する人が証明するべきなのに、それを相手に押しつけると不公平な議論になってしまいます。
だからこそ、「それって本当に自分が証明すべきことなのか?」と考える力が大切です。
この考え方を知っておくことで、SNSや会話の中でも冷静に対応できるようになりますよ。