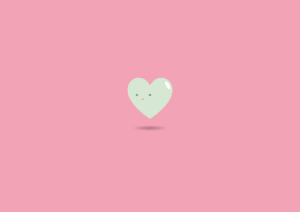ハロウィンよりもずっと前から、日本にも「お菓子をもらう夜」があったことをご存じですか?
それが「お月見どろぼう」…!
毎年十五夜に合わせて子どもたちが家々を訪ね歩く風習で、今も一部の地域で受け継がれています。
今回はそんな「お月見どろぼう」について、具体的にいつどのように行われるのか解説していきます。
「お月見どろぼう」とは?2025年の十五夜はいつ?

「お月見どろぼう」とは、旧暦8月15日の十五夜(中秋の名月)の日に飾られているお月見のお供え物(お団子)を、子どもたちが盗むという風習です。
この十五夜の日に限っては「盗む」という行為が許されており、地域によっては他の家庭を回って盗みにいくのも良しとされ、お供えする側も盗みやすい位置にお供えするなどして工夫しています。
2025年の十五夜は10月6日(月)ですので、「お月見どろぼう」もこの日に行われます。
お供え物には、お団子以外にも子どもたちが好むお菓子などもあるため、子どもたちにとっても「お月見どろぼう」は楽しみな行事の一つとなっているでしょう。

「お月見どろぼう」の発祥・由来は?

お月見どろぼうの発祥や由来を明確に記すものはありませんが、江戸時代ごろからあったとされています。
また、諸説あったり時代の流れで変化してきたものもあったりするので、それぞれご紹介します。
「子どもは月からの使者」という考え
昔、子どもたちは“月からの使者”と考えられていました。
子どもたちは竿のような長い棒の先に釘や針金をつけて、十五夜にお月見のお団子を盗んだそうです。
これを大人は「お月様がお供えを受け入れてくださった」「お月様が持っていってくださった」と捉え、盗まれれば盗まれるほどその家は豊作になるとして、縁起が良いと喜ばれました。
「お月見どろぼう」は畑の芋を盗んでもらうことが発祥?
昔、十五夜(中秋の名月)の日だけは、他人の畑の芋(里芋やサツマイモ等)を盗んでも良いという風習がありました。
これも、先ほどご紹介した「子どもは月からの使者」という考え方と同じように、「お月様が持っていってくださった」という意味で縁起が良く、“芋を盗まれた畑は豊作になる”と言われていたようです。
どことなくお月見どろぼうと似ていますね。
しかし、取れるだけ取りまくるのではなく、「道から片足だけ踏み込んだ範囲のみ」という暗黙の了解のもと。
月の満ち欠けが農作物の出来に影響すること、そして旧暦8月が芋の収穫時期であったことから、十五夜は芋の収穫祭でもあります。
お月見が農耕行事とも結びつくことから、お月見は名月を愛でるだけでなく、「収穫に感謝して自然の恵みや秋の実りはみんなで分かち合おう」という意味も込められています。
そのため、お月見にはお団子のほかにも、芋や栗、柿や枝豆といった秋の収穫物をお供えする地域や家庭もあります。
こうしたことから、十五夜を「芋名月」とも呼ぶようです。
そしていつからか、盗む対象が畑の芋からお月見のお供え物(お団子)へと変化していきました。
現在でも「お月見どろぼう」が行われている地域はどこ?
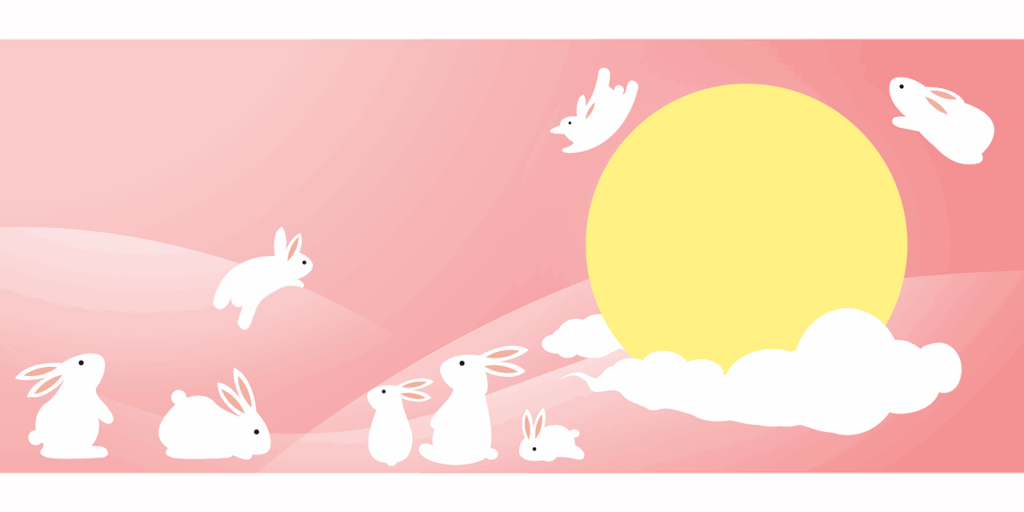
お月見どろぼうは現在でも一部の地域で、子どもたちが「お月見どろぼうでーす」「お月見くださーい」などと言いながら、各家を回ってお団子やお菓子をもらう風習として続いています。
特に愛知県名古屋市・日進市、三重県四日市市では、お月見どろぼうの風習が強く残っているようです。
ほかにも福島県いわき市、岐阜県恵那市、三重県四日市市、奈良県生駒市、大分県大分市、大阪府四条畷市などでも名残があります。
ただ、お月見どろぼうの伝統は少しずつ減っていき、今では風習を知らない人たちも多くいるのです。
お月見当日は、玄関や軒先に”お月見どろぼうさん、お一つどうぞ”というメッセージとともに、かごに入ったお団子やお菓子が準備されています。
「お月見どろぼう」はハロウィンと似ている?

お月見どろぼうは、どことなくハロウィンと似ていませんか?
ハロウィンは、キリスト教の祝日である「万聖節」前夜に行われるお祭りのことで、起源は2000年以上前の古代ケルト人まで遡ります。
古代ケルト人にとって一年の終わりは10月31日で、この日に収穫祭を行うのが通例でした。
それと同時に、一年最後の日は日本のお盆と同じようにご先祖様などが現世へ戻ってくると言われ、一緒に死者の霊も戻ってきて子どもの魂を取ってしまうこともあるとされていました。
そこで人々は、悪霊を怖がらせて去ってもらうために仮装を始めたのです。
お菓子を配るのも、悪霊に悪さをさせず、ご機嫌の状態で出ていってもらうためだとされており、そこから現代の「トリック・オア・トリート!(Trick or Treat!)」に変化していきました。
「悪霊退散」と「豊作を願って」では目的が異なりますが、子どもたちが食べ物をもらって楽しめるイベント、という意味ではお月見どろぼうと似ているといえますね。
ちなみに、お月見どろぼうは「和製ハロウィン」「日本版ハロウィン」とも呼ばれることがあるようです。
まとめ
「お月見どろぼう」についてご紹介しました。
お月見どろぼうは、日本に古くから伝わる秋の風習です。
「月からの使者が来ると縁起が良い」という考え方が背景にあり、訪ねてきた子どもに食べ物を渡すことで、その年の実りに感謝し翌年の豊作を願いました。
そして今もなお、一部の地域では大切な伝統行事として残っています。
2025年の十五夜は、そんなお月見どろぼうのことを想いながら、過ごしてみてはいかがでしょうか?