みなさんは、5月といえば何をイメージしますか?
きっと一番に思い浮かぶのは、多くの方にとっては5月最大の魅力、GW(ゴールデンウィーク)でしょう。
この記事では、5月のシンボルやイメージするもの、5月にあるさまざまなものを深堀していきたいと思います!
ぜひ、暇つぶしがてら知識を増やして、日常会話のネタにしてみませんか?
5月の祝日と主な記念日

5月の祝日は3日に憲法記念日、4日にみどりの日、そして5日にこどもの日があります。
学生や(カレンダー通りの出勤形態の)社会人にとって嬉しい、GW(ゴールデンウィーク)ですね。
次に、5月の記念日について31日分ご紹介します。
1日 恋が始まる日
2日 コージーコーナーの日
3日 世界報道自由デー
4日 ラムネの日
5日 甘党男子の日
6日 コロッケの日
7日 博士の日
8日 世界赤十字デー
9日 アイスクリームの日
10日 リプトンの日
11日 ご当地キャラの日
12日 ナイチンゲールデー
13日 カクテルの日
14日 温度計の日
15日 沖縄本土復帰記念日
16日 旅の日
17日 お茶漬けの日
18日 国際博物館の日
19日 ボクシングの日
20日 世界ミツバチの日
21日 小学校開校の日
22日 ガールスカウトの日
23日 ラブレターの日
24日 ゴルフ場記念日
25日 納本制度の日
26日 メープルもみじの日
27日 百人一首の日
28日 花火の日
29日 幸福の日
30日 ごみゼロの日
31日 世界禁煙デー
5月の満月|フラワームーン

5月の満月の名前は「フラワームーン(花月)」といいます。
名前の由来は、5月は気候が暖かくなり、たくさんの花が咲く時期であることだと言われています。
フラワームーンは、恋愛運や対人関係運などを良くするというジンクスがあるのだそう!
人間関係に変化をもたらしたいと考えている方は、お願いをしてみてはいかがでしょうか?
2025年のフラワームーンは、5月12日~13日にかけて(完全に見えるのは13日の1時56分頃)です。
ちなみに当日には、フラワームーンの写真をお守りにしたり、お花を飾ってリラックスタイムを作ると、より効果が得られやすくなるようですよ◎
5月の誕生花と時期の花・植物

5月の誕生月花は、白い鈴のような形の可憐な花を垂れ下げる姿が特徴的な「スズラン」です。
花言葉は「再び幸せが訪れる」「純粋」「溢れる美しさ」「謙虚」で、ヨーロッパでは聖母マリアを象徴する花として尊ばれています。
フランスでは5月1日を「スズランの日」とし、愛する人や感謝したい人にスズランを贈る習慣があり、贈られた人に幸福が訪れるとされています。
5月に咲く花や植物は以下のようなものがあります。
・バラ(花言葉:愛、美)
・ハナミズキ(花言葉:返礼、永続性)
・ビバーナムスノーボール(花言葉:茶目っ気、誓い)
・ハニーサックル(花言葉:献身的な愛、愛の絆、友愛)
・エゴノキ(花言葉:壮大)
・ハクウンボク(花言葉:壮大、愛の旅、朗らかな人)
・カルミア(花言葉:優美な女性、大きな希望、野心)
・ポピー(花言葉:思いやり、労り、恋の予感、陽気で優しい)
・ゲラニウム(花言葉:陽気、変わらぬ信頼、友情)
・クレマチス(花言葉:精神の美、旅人の喜び、策略)
・シャクヤク(花言葉:恥じらい、慎ましさ、華麗、はにかみ)
・カモミール(花言葉:逆境に耐える力、エネルギー、癒し)
・ネモフィラ(花言葉:どこでも成功、許す、可憐)
・かすみ草(花言葉:感謝、清らかな心、無垢の愛)
~5月の誕生石と意味

5月の誕生石は「エメラルド」と「翡翠(ひすい)」です。
それぞれの特徴を見ていきましょう。
エメラルド
エメラルドはベリルという鉱物に属します。
紀元前4000年以上前の古代エジプトで珍重されており、その輝きから「緑の火」とも呼ばれとても大切にされてきました。
モース硬度では硬い部類に入りますが、衝撃に弱く割れやすい性質のため、耐久性を強化して美しく発色するように特殊なオイル処理がされているのです。
名前の語源は諸説ありますが、一番初めの「スマラグドス(ラテン語)」からいくつもの遍歴を辿り、現在の「エメラルド(英語)」へ落ち着いたと言われています。
石言葉は「愛」「夫婦愛」「幸福」「希望」などがあり、エメラルドを身につけると、知恵や忍耐力が備わるとされているんですよ。
翡翠(ヒスイ)
翡翠は鮮やかな緑色を想像する方が多いかもしれませんが、本来の色は無色透明です。
さまざまな鉱物が集まってできた宝石なので、構成されている鉱物の色や成分によって色が変わったり、肌に触れると油分と馴染み艶が増していくのが特徴となります。
翡翠には精神的な安定と心の平和をもたらしてくれる効果があり、また持つ人にポジティブなエネルギーを与えてくれます。
また、成功と繁栄という効果もあり、社会的地位にある方や富裕層にも人気がある石です。
これらからなんとなく想像できますが、石言葉は「平穏」「長寿」「調和」「幸福」「友情」などで、大切な人への健康と幸運を願うための贈り物として選ばれることが多いです。
美味しく食べよう!5月が旬の野菜

5月の旬の主な野菜は、新玉ねぎ、じゃがいも、そらまめ、わらびなどです。
新玉ねぎ
新玉ねぎは皮が薄く、水分が多くて柔らかいのが特徴です。
味や栄養素などの良さを生かすには、炒め物よりもサラダやスープにして食べるのが◎
じゃがいも
5月の新じゃがは、普通のじゃがいもと比べてビタミンCがたっぷりで、水分が多く柔らかいのが特徴です。
皮が薄いため、綺麗に洗えばそのまま調理することもできますので、余すことなく食しましょう!
そらまめ
この時期に旬のそら豆は、塩で茹でたりトースターで焼くと美味しく食べることができ、おつまみにもぴったりですね。
選ぶ際は、鮮やかで豆の形が整っているものを探すと◎
わらび
山菜の女王と呼ばれるこの時期のわらびは、栄養素が高く食物繊維やミネラルを豊富に含んでいます。
また、カリウムや鉄分も多く含んでいることから、貧血予防にもおすすめです。
調理法としては、シンプルなおひたしやソテー、パスタに加えても良いでしょう。
5月が旬の果物

5月の旬の果物の代表は、マンゴー、メロン、さくらんぼ、梅です!
マンゴー
初夏の気候になる5月に旬を迎えるマンゴーは、国産のものだとアップルマンゴーと言われ、完熟すると皮が赤くなる品種が多いです。
とても濃厚な甘さと柔らかな酸味が絶妙のバランスで美味しいですよ。
メロン
メロンの品種の種類は多く、果肉の色や香り、味わいなどの特徴はさまざまです。
安価なものでも、旬のメロンはジューシーで甘みを感じることができるのでおすすめです。
さくらんぼ
さくらんぼは日本のものだけでも100種類ほどあると言われており、その中でも鮮やかな紅色の「佐藤錦」は果肉や果汁が多く、甘いため非常に人気です。
そのまま食べるのはもちろん、ケーキやヨーグルトと一緒に食べるのもおすすめです。
梅
熟する前の青梅は5月に出回ります。
爽やかな酸味と風味が特徴の青梅は、梅シロップや梅ジュース、梅酒作りに向いています。
また、完熟すると果肉が柔らかくなり甘みが出るので、梅干しやジャムにすると良さを生かすことができますよ。
5月を表す言葉って知ってる?季語も紹介
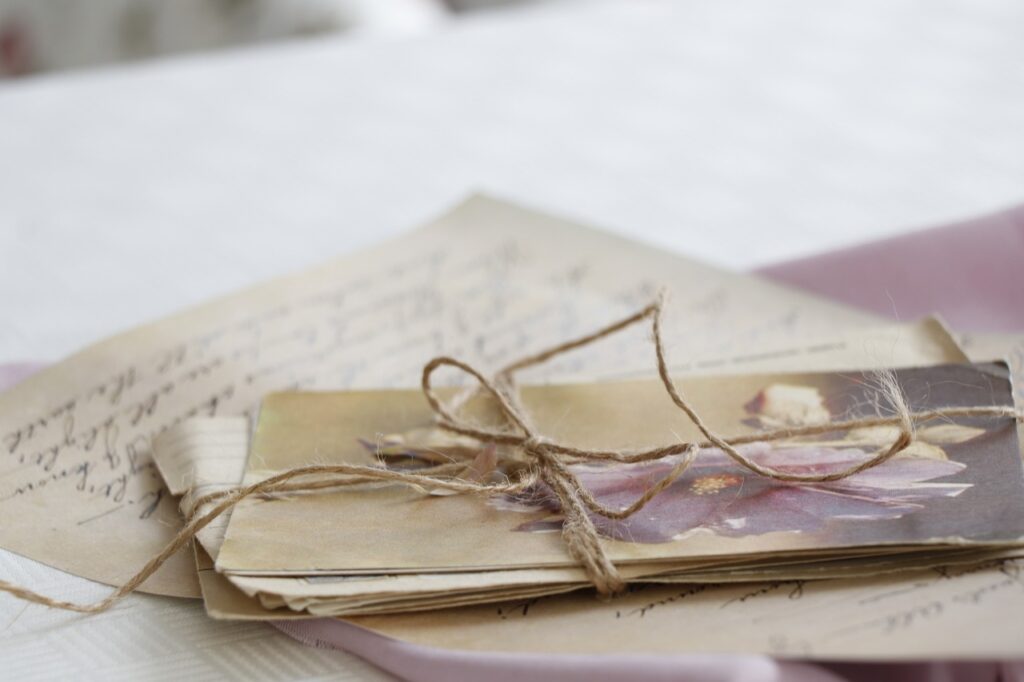
5月を表す言葉と意味・由来
| 言葉 | 意味・由来 |
| 皐月(さつき) | 「皐」は稲作や田の神様、神に捧げる稲という意味。作の月、田んぼに早苗を植える月であることから。 |
| 建午月(けんごげつ) | 古代中国では冬至を含む月に、北斗七星の取っ手の先が真下(北の方角)を指すため、11月を十二支の最初である建子月とした。それから順に数えて5月は「建午月」とする。 |
| 雨月(うげつ) | 旧暦の5月は現在の6月、つまり梅雨時期にあたるため。 |
| 仲夏(ちゅうか) | 陰暦の夏である4・5・6月の、真ん中の月であることから。 |
| 橘月(たちばなづき) | 橘の花が咲くため |
5月の季語
季語とは、歌や俳句を詠む時に中に入れる語句を言います。
5月の季語には、以下のようなものがあります。
風薫る、新緑、木の芽流し、柏餅、麦飯、新茶、五月雨、青葉潮、夏めく、藤波、鯉のぼり…。
爽やかなものや、こどもの日をイメージするものが多いですね。
時候のあいさつ
| あいさつ | 意味 |
| 新緑(しんりょく) | 濃くなってきた初夏の緑の爽やかな印象 |
| 若葉(わかば) | 出始めた緑が生き生きとしている様子 |
| 立夏(りっか) | 二十四節季「立夏」に合わせて |
| 薫風(くんぷう) | 初夏の香り立つ風、爽やかな風 |
| 青葉(あおば) | 青々とした木々の葉が生い茂る季節 |
| 惜春(せきしゅん) | 過ぎ行く春を惜しむ季節 |
5月をイメージする色は?
5月といえば、何色をイメージしますか?
ここでは、5月のイメージカラーをご紹介しますので、洋服や持ち物などに取り入れてみてくださいね。
藤色:藤の花をイメージする色
勿忘草色(わすれなぐさいろ):紫がかった薄い青色
苗色:苗をイメージする黄緑色
若竹色:若竹の幹のような明るい緑色
卯の花色:ほのかに黄色がかった白
山吹色:赤みを含んだ濃い黄色
石竹色:石竹はナデシコ科の花で、優しい紅色
5月に楽しみなイベントは?

GW(ゴールデンウィーク)
5月といえばGWでしょう。
3日:憲法記念日
4日:みどりの日
5日:こどもの日
この3日間に土日がうまく合わさると5日ほどの連休となり、学生さんや社会人のみなさんにとって待ちに待った最高の休暇となります。
ただ社会人は、職場によってはカレンダー通りの休みでなく、GW関係なく出勤される方や、反対に4月の下旬から1週間~10日間の休みとなる方など、さまざまでしょう。
どちらにせよ、勉強や仕事、人間関係の疲れなどから少し離れて、ゆっくり羽を伸ばせる日になれば良いですね。
こどもの日
お子さんがいる家庭では、兜や鯉のぼりを飾ったり、柏餅やちまきを食べたりするのでしょうか。
ちなみに柏餅は「子孫繫栄」、ちまきには「無病息災」の意味が込められているようです。
母の日
毎年、第2日曜日は「母の日」です。
日頃の感謝の気持ちを込めて、「ありがとう」を伝えたり、カーネーションをはじめとする花やプレゼントを贈ったりする日となっています。
母の日の起源は、今から100年以上前にアメリカの提唱者、アンナ・ジャービスさんが母を追悼するため、教会で白いカーネーションを配ったことだとされています。
まとめ
いかがでしたか?
5月の特徴・象徴するものなどをご紹介しました。
新たに知ったものはありましたか?
5月ならではの食べ物や行事を、ぜひ楽しんでくださいね。


