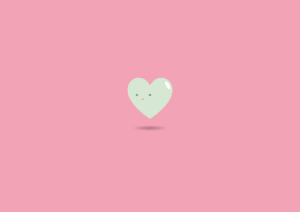「いろはにほへとちりぬるを」
『いろは歌』のはじめの一節、日本人ならだれでも知ってるフレーズでしょう。
これには続きがあるのをご存知でしょうか?
実は『いろは歌』の意味には、とても深く趣のある意味が隠されているのです。
この記事では、いろは歌の全文の意味や作られた背景、英語版について解説していきます。
「いろはにほへとちりぬるを」は日本の伝統的な『いろは歌』

『いろは歌』とは、仮名文字47字を1回ずつ使って作られた韻文(「パングラム:すべての文字を使用して作られた文章」)で、さらに七五を4回繰り返す「今洋(いまよう)」という歌謡形式で作られています。
限られた文字、つまり一度も仮名を重複させることなく五七調に乗せ、しっかり意味を持たせたというのは、すごいことですよね。
これも、”行間を読む”という文化のある日本語だからこそ感じられる魅力でしょう。
また、『いろは歌』の背景には仏教的な思想が関係しており、特に“無常観”や“人生の儚さ”を表しています。
江戸時代は庶民に読み書きを教える寺子屋で使われた教材の一つでしたが、当時の人たちにとっては、単なる文字だけでなく人生についても学ぶことのできる教材でもあったと言えるでしょう。
ちなみにこの『いろは歌』、10世紀後半から11世紀半ば頃に誕生したとされ、作者は不明ですが、昔から平安時代の「弘法大師空海」説が広く流布していました。
しかし空海の時代には、七五調の4句で構成される形式の韻文がまだ存在しなかったということや、国語的な観点などから、現在は否定されています。
近年は飛鳥時代の歌人、「柿本人麻呂」という説も出てきていますが、やはり作者は不明のままです。
どちらにせよ、『いろは歌』は『金光明最勝王経音義』という経典に残っており、今もなお広く語り継がれています。
「いろはにほへとちりぬるを」の続きは?全文の意味や漢字を解説
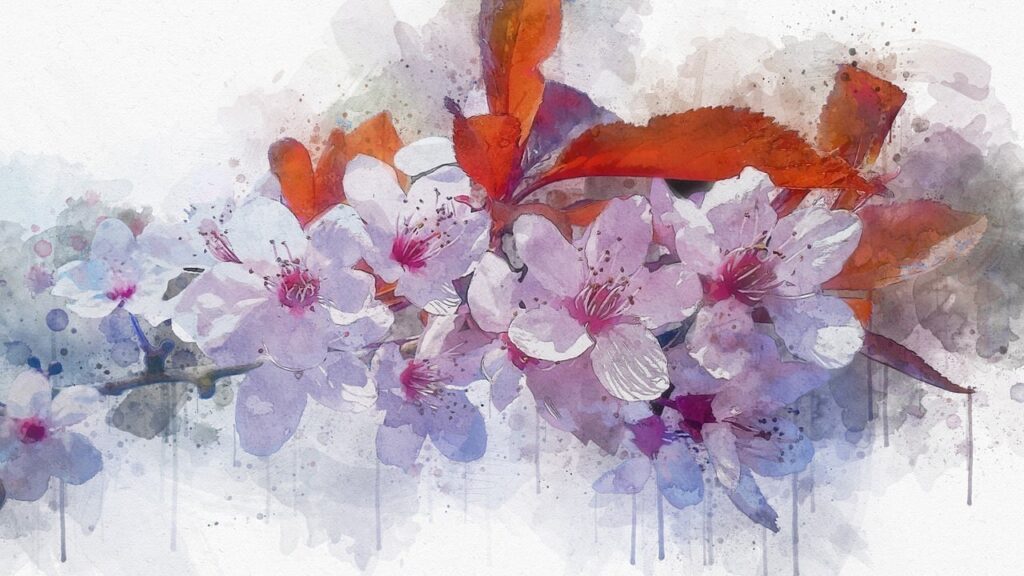
「いろはにほへとちりぬるを」の全文をご存知ですか?
ここでは前文とその漢字、意味をご紹介します。
『いろは歌』いろはにほへとちりぬるを|全文紹介(漢字・読み方)
『いろは歌』の全文と漢字は以下のような文になっています。
いろはにほへと ちりぬるを
『色は匂へど 散りぬるを』
わかよたれそ つねならむ
『我が世誰ぞ 常ならん』
うゐのおくやま けふこえて
『有為の奥山 今日超えて』
あさきゆめみし ゑひもせず
『浅き夢見し 酔いもせず』
いろはにほへとちりぬるを|全文の意味と解説
いろはにほへと ちりぬるを
『色は匂へど 散りぬるを』
「花は咲いて散ってしまうのに(花は美しく咲き誇っても、やがては散ってしまう)」
※色=桜の花(意:花が匂うほど咲き誇る)
わかよたれそ つねならむ
『我が世誰ぞ 常ならん』
「永遠に同じ姿でこの世に居続ける人も物もない(いったいこの世の中で、永遠に変わらないものがあるだろうか。いや、そんなものはない|一体この世で永遠に生き続けることのできる人はいるのだろうか。いや、いない)」
※ぞ~む=○○な人が本当にいると思う?いないよね。
うゐのおくやま けふこえて
『有為の奥山 今日超えて』
「つらく厳しく険しい人生という山を、今日も一つ乗り越えて(迷いの多い人生の深い山を、今日乗り越えて)」
※有為=移り変わるこの世のすべての現象、奥山=深い山(意:迷いや苦しみが多い人生の険しい道)
あさきゆめみし ゑひもせず
『浅き夢見し 酔いもせず』
「酔っぱらっているかのように真理から目を背け、儚い夢を見ないように(儚い夢を見たり、快楽に酔いしれたりすることもなく)」
※酔う=お酒ではなくお金や地位、名誉などの煩悩に近い
『いろは歌(いろはにほへとちりぬるを)』のもとになったものがある?

『いろは歌』である「いろはにほへとちりぬるを」には、元となったものがあるとされています。
それは、仏教のお経「涅槃経(ねはんぎょう)」。
涅槃経も無常観(すべてのものは変化し、人の世もまた儚いものである)を説いていることから、これを日本語訳にしたのではないかと言われています。
諸行無常(諸行は無常なり)⇒『色は匂へど 散りぬるを』
是正滅法(是れ生滅の法なり)⇒『我が世誰ぞ 常ならん』
生滅滅巳(生滅滅しおわりぬ)⇒『有為の奥山 今日超えて』
寂滅為楽(寂滅をもって楽と為す)⇒『浅き夢見し 酔いもせず』
訳:この世のすべては移り変わる(続かない)。形あるものは必ず壊れ、出会った人とは必ず別れが来る。この世のすべては生じたら必ず滅するものであるから。これは変わることのない真理だ。生きることと死ぬこと、生と滅を超越したところに、永遠の安らぎ(幸せ)の世界がある。
パングラム「the quick brown fox jumps over the lazy dog 」|「いろはにほへとちりぬるを」英語ver.

『いろは歌』には、実は英語バージョンもあるのをご存知でしょうか?
「the(a) quick brown fox jumps over the lazy dog 」
和訳:素早い茶色のキツネは、のろまな犬を飛び越える
これは、すべてのアルファベット(26文字)を使用して作られているパングラムの中で、最も有名な文章です。
ただ、日本のいろは歌のように文章そのものに意味はありません。
一般的にはタイピングの練習や試験、データ通信(PC)で正確に遅れるかどうかという試験、フォントの表示例などに使われ、「quick brown fox」や「Fox Massage」と省略されることもあります。
まとめ|「いろはにほへとちりぬるを」は仏教的背景のあるパングラム!
『いろは歌(いろはにほへとちりぬるを)』には、仏教的な背景があり、世の中や人生の無常観・儚さが込められていることが分かりました。
47字を重複させずにすべて使い、こんな素敵な意味を表現できるんですね。
作者は分かりませんが、そのことがさらにこの『いろは歌』の魅力を引き立てているのかもしれません。
今回は以上です。最後までご覧いただきありがとうございました。