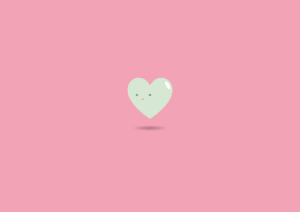9月になるとふと、「今年の十五夜はいつだろう」と考える人もいるのではないでしょうか?
毎年変わる十五夜は、日本人が昔から愛でてきた特別な日です。
お月見団子やススキを飾り、豊作や健康を願う…そんな風習には、四季とともに暮らしてきた人々の想いが込められています。
今回は、そんな十五夜の由来や意味などを解説していきます。
十五夜とはどんな意味がある?2025年はいつ?

十五夜の意味は?2025年はいつ?
十五夜の日は旧暦に基づいて毎年変わるため、「今年はいつだろう」と思う方がいるでしょう。
結論から言うと、2025年の十五夜は10月6日(月)です。
ちなみに昨年は9月17日(火)でしたので、ずいぶんと幅がありますね。
十五夜とは本来、旧暦における毎月15日の夜のことで、一般的にお月見をする十五夜は旧暦8月15日を指します。
そしてお月見をする十五夜は、1年で最も美しいとされる中秋の名月を鑑賞しながら、秋の収穫に感謝をする行事のことです。
十五夜の由来は中国の「中秋節(ちゅうしゅうせつ)」
十五夜にお月見をする風習は、中国に起源があるとされています。
中国では古くから、旧暦の8月15日に秋の中心を祝う「中秋節(ちゅうしゅうせつ)」という、月を祀る行事が行われています。
中秋節は、春節・端午節と並ぶ中国の祝日で、遠くに住む家族や親戚が一堂に会する大切な日です。
中秋節では、家族で月を見ながら月に見立てた丸く平たい形の「月餅(げっぺい)」という、堅めの生地にあんこが入ったお菓子を食べて幸福を祈るそうです。
この中秋節が平安時代に日本へと伝わり、十五夜として定着したと言われています。
コンビニの「月餅(げっぺい)」食べてみた!
中国が中秋節に食べる「月餅(げっぺい)」がコンビニ(今回はセブンイレブン)に売っていたので、食べてみました。

山崎製パンの「特選 月餅」。
丸にほんのりお花型に切れ込みが入った形のお菓子です。
コンビニだけでなくスーパーにも並んでいて、おそらく十五夜の時期に限らず一年を通して販売しています。

切ってみると、薄い生地の中にあんこがぎっしりと詰まっていて、ほんの少しクルミも混じっています。
生地はしっかりめで、こしあんは甘さ控えめなのでたっぷり入っていてもくどさを感じません。
小さく砕かれたクルミは、ほんのり香ばしくて食感とともにあんこと良く合います。
中国本場の月餅を食べたことがないので比較はできませんが、これはこれとしてとても美味しかったです!
和菓子が好きな方はぜひ見つけてみてください。
十五夜と「中秋の名月」との違いは?

旧暦では7~9月が秋とされており、秋の真ん中の8月15日は「中秋」と呼ばれます。
そして中秋の月は、一年で最も美しく映ることから「中秋の名月」と呼ばれているのです。
秋の夜空は空気が澄んでいて月がとてもよく見えますが、その中でも特に中秋の名月は群を抜いて綺麗に見えるとされています。
今では十五夜=中秋の名月とされることが多くなっていますが、本来の意味としては十五夜は「旧暦15日のすべての夜」、中秋の名月は「月」を指すのです。
十五夜に供える食べ物といえば、やっぱり月見団子!

昔から月見団子が供えられていた?
十五夜に供える食べ物と言えば、やはり「月見団子」でしょう。
十五夜の時期になると、スーパーやコンビニ、和菓子屋さんなどで月見団子を見かけるようになります。
月見団子を供える風習の起源は、十五夜の由来でご説明した通り中国の中秋節にありますが、昔はお団子ではなく芋や豆を供えていたそうです。
これは、月の満ち欠けが農作物の出来に影響すると考えられていたため。
秋は農作物の収穫期で、月に豊作の感謝の意を表すために十五夜に収穫した芋や豆を供えていました。
それがいつしか、月に見立てた月見団子に代わっていったのです。
月見団子にはどんな意味や種類がある?
十五夜に供える月見団子は、ピラミッド型が定番でしょう。
これにもきちんと意味があります。
月見団子を重ね、一番上の団子を天に向けることで、作物への感謝や来年の豊作への祈りを、月に届けようということです。
また、月見団子を食べることで、月から健康や幸せを分け与えてもらえると信じられていました。
月見団子の数は、十五夜にちなんで15個にするのが一般的ですが、地域や家庭によって1年の満月数に合わせて12個にしたり、5個や10個など食べきれる数にしたりとさまざまです。
地域ごとの月見団子
さて、みなさんが十五夜でイメージする月見団子は、何ものっていないシンプルなまんまる団子が多いかもしれませんが、これは主に関東圏でのもので、実際は地域によってさまざまなお団子が供えられます。
たとえば関西では、秋に収穫する里芋をイメージして、しずく型の団子にあんこをかぶせて作られます。
静岡県のお団子は「へそもち」と言い、平たくつぶされたお団子の真ん中をへこませ、そこに餡をのせて食べるそうです。
また、沖縄県では「ふちゃぎ」といって、小判型のお餅の周りに塩ゆでした小豆がびっしりと覆っています。
このように、十五夜では地域によってさまざまな月見団子があるのも、面白いですね。

十五夜にはなぜススキを供えるの?

十五夜といえば、お団子のほかにもう一つ、「ススキ」ではないでしょうか。
ススキは「秋の七草」に入るほど秋を代表するものです。
十五夜にススキを供えるのはいくつか理由があります。
①邪気を払うため
②神様の依り代であるため
③秋の実りに感謝して愛でるため
まず、昔はススキの棘には邪気を払う力があると信じられていたことから、災いや病などから作物や家を守ってもらうこと、そして豊作を願っていたのです。
また同じく昔は、背の高い稲穂は神様の依り代だとされていました。
しかし、十五夜の時期はまだ穂が実らないため、形が似ているススキを代わりに、神様に供えていました。
それから、十五夜にススキを供えるのには、昔からの”十五夜は秋の実りに感謝する”という風習ともつながっています。
丸い団子を満月、そしてススキを稲穂に見立てることで、秋の収穫物に感謝し月を愛でるのです。

お月見は十五夜だけじゃない!「十三夜」「十日日(とおかんや)」って知ってる?

十三夜
「十三夜」は聞いたことがある方もいるかもしれません。
十三夜とは、旧暦の9月13日の夜に行われるお月見のことを言い、今年は11月2日(日)です。
十三夜は「十三夜の月は十五夜に次いで美しい」とされており、昔から大切にされてきた日本発祥の行事だと考えられています。
お米で作った団子に加え、栗や豆の収穫に感謝し供えることから、「栗名月」「豆名月」とも呼ばれているのです。
十五夜のように秋の実りに感謝するため、月見団子を食べススキを飾り、来年の豊作を願います。
十日夜(とおかんや)
「十日夜(とおかんや)」は、旧暦10月10日のことで、今年は11月29日(土)にあたります。
この日は、稲の刈り取りが終わり田んぼの神様が山に帰るとされているため、田んぼの神様に感謝する日なのです。
十日夜も十五夜・十三夜と同じく月見をする風習があり、主に東日本を中心に行われており、別名「刈り上げ十日」とも言います。
餅つきをしたり、子どもたちが藁を束ねて作った「藁鉄砲」で地面を叩き、作物に悪さをするモグラを追い払ったりするのが通例行事となっているようです。
また、十日夜は地域によって「亥の子」「案山子上げ」「大根の年取り」などと異なる名称があり、風習にも個性があります。
どの地域も、さまざまな方法で次の年の豊穣を祈願する大切な行事となっているのです。
まとめ
十五夜についてご紹介しました。
2025年の十五夜は10月6日(月)です!
十五夜は月を愛でるだけでなく、自然や季節の恵みに感謝する日でもあります。
今年は秋の実りに感謝をして、月を眺めながらお月見団子を食べてみませんか?