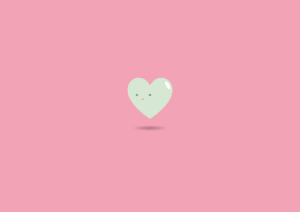「七草」といえば春を連想する方が多いかもしれませんが、実は秋にも七草があるのをご存知でしょうか?
秋の訪れを告げる「秋の七草」は、春の七草とは違い鑑賞を目的としています。
今回は、奈良時代から歌に詠まれ、私たちの生活に癒しと彩を加えてきた「秋の七草」の由来や名前の覚え方、各草花の特徴を解説していきます。
秋の七草の種類や名前とは?

秋の七草とは、秋を代表する以下の7種類の草花の総称です。
「萩・尾花(ススキ)・葛・撫子・女郎花・藤袴・桔梗」
ここでは、由来や春の七草との違いを解説していきます。
秋の七草の起源は万葉集にある!
秋の七草の起源は、万葉集に登場する”山上憶良”の歌にあります。
「秋の野に 咲きたる花を 指折り(およびをり) かき数ふれば 七草の花」
⇒意:秋の野に咲いている花を指折り数えてみれば、7種の草花がありました。
「萩の花 尾花 葛花 なでしこの花 女郎花また藤袴 朝貌(あさがお)の花」
⇒秋の七草をならべています。
ここで出てくる「朝貌」には諸説ありますが、一般的に言う「朝顔」ではないとされています。
なぜなら、万葉集が完成した7世紀後半から8世紀後半の頃は日本にはまだ「朝顔」はなく、朝に咲く花を総称して「朝貌」と呼んでいたためだそうです。
そして、ここでいう「朝貌」は”桔梗”が有力説だと分かっています。
春の七草とは目的が違う
秋の七草といえば、同時に「春の七草」も頭に浮かびますが、実は秋と春では目的が異なるのです。
春の七草(せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな、すずしろ)は、行事食として「七草がゆ」を食べて楽しむというイメージがありませんか?
毎年1月7日の人日(じんじつ)に、邪気を払い一年の無病息災を願うことを目的に、七草がゆを食べますね。
一方で秋の七草は、食用ではなく「観賞」としての位置づけ!
季節の風物詩である秋の草花を眺めて、楽しむことを目的としています。
また、食用ではないものの、漢方や薬として利用できるものもあり、昔から親しまれてきました。
秋の七草一覧|それぞれの特徴と花言葉

萩(はぎ)
「萩」は、マメ科ハギ属の総称で、秋の到来を告げる代表的な草花です。
しなやかな枝と小さな紅紫色の花が風に揺れる姿が、なんとも風情があって素敵ですね。
「萩」という漢字は日本で作られた”和製漢字”と呼ばれており、「草冠+秋」の組み合わせが、日本人が古くから萩を秋の花として大切にしてきた様子が伝わります。
万葉集にも多く登場し、古くから日本人に愛されていますよ。
花言葉:「想い」「思案」「内気」
尾花(おばな/ススキ)
「尾花」はイネ科の多年草で、ススキの別名です。
ススキはすくすくと育つので、「スクキ」→「ススキ」になったと言われています。
尾花は山火事があってもいの一番に再生すると言われるほど、生命力の高い植物です。
黄金色の穂が風になびく姿はまさに秋の風物詩で、十五夜のお月見に欠かせません。
また、姿かたちが稲穂に似ていることから、豊作の象徴ともされます。
花言葉:「活力」「精力」
葛(くず)
「葛」はマメ科・クズ科のツル植物で、蔓を長く伸ばし紫色の花を咲かせます。
根から取れる澱粉は「葛粉」として和菓子の材料として利用され、根を乾燥させると「葛根湯(かっこんとう)」という薬になり、解熱剤や鎮静剤として使われます。
また、中国では古くから二日酔い予防にも利用されてきたとされています。
このように、葛は観賞用としてだけでなく、さまざまな分野で役に立つ植物としても重宝されてきました。
花言葉:「根気」「活力」「努力」「芯の強さ」「治療」
撫子(なでしこ)
「撫子」はナデシコ科の多年草で、細い花びらが愛らしいピンク色の花です。
「撫でてあげたいくらい可愛い花」という意味で名づけられたとされています。
「大和撫子」という言葉の由来にもなり、日本女性の奥ゆかしさや美しさを象徴します。
花言葉も女性をイメージするものが多いです。
花言葉:「大胆」「純愛」「貞節」「いつも愛して」
女郎花(おみなえし)
「女郎花」はオミナエシ科の多年草で、日当たりの良い山野で見ることができます。
小さな黄色い花がまとまって咲く姿が特徴的で、古くは女性の美しさを引き立てるとして親しまれた花です。
乾燥させて煎じたものは「敗醤(はいしょう)」という薬になり、平安時代以前から解熱剤や解毒剤として活用されてきました。
花言葉:「美人」「儚い恋」「親切」「忍耐」
藤袴(ふじばかま)
「藤袴」はキク科の多年草で、河原や湿った草原などで薄ピンク色の小花を咲かせます。
『源氏物語』や『徒然草』にも登場し、昔から親しまれてきた花の一つです。
乾燥させた葉は優しく甘い香りが魅力で、平安時代には香りを衣に移したり、匂い袋や洗髪などに活用したりして楽しんだとされてます。
現在は野生のものを見ることは少なくなっており、絶滅危惧に指定されています。
花言葉:「躊躇(ためらい)」「遅れ」「やさしい思い出」
桔梗(ききょう)
「桔梗」はキキョウ科の多年草で、星型が特徴的な紫や白、ピンク色の花を咲かせます。
古くから薬草(漢方)としても用いられ、武士の家紋にも使われていました。
現在は園芸用はあるものの、野生のものはあまり見られなくなり、絶滅危惧であるとのことです。
花言葉:「永遠の愛」「誠実」「清楚」「気品」「従順」
秋の七草の覚え方|名前の順番を複数紹介
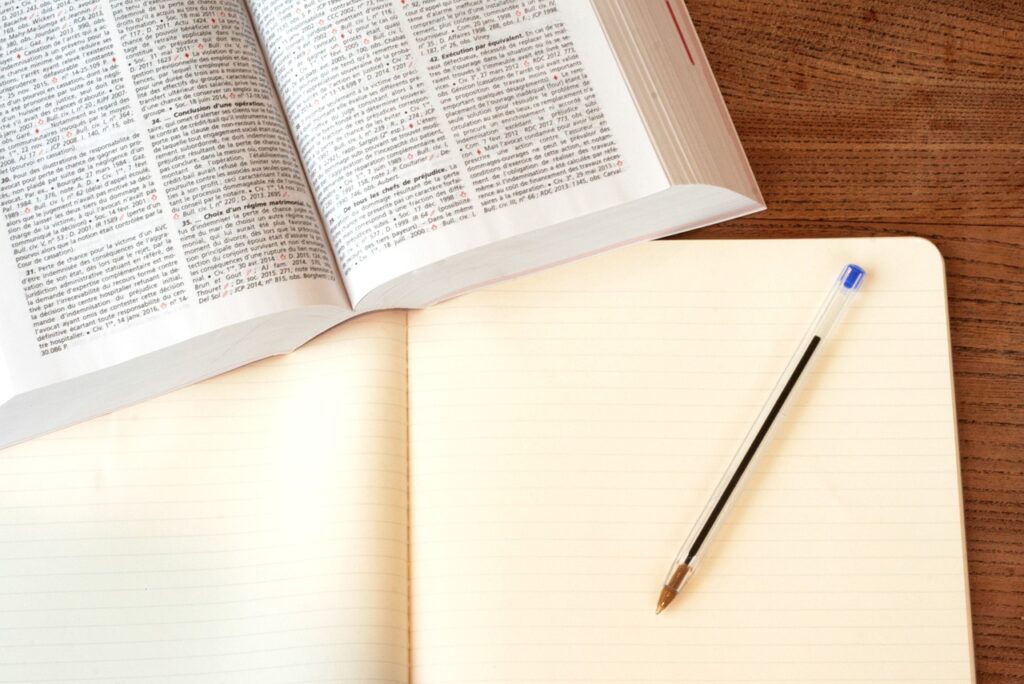
五・七・五・七・七のリズムで覚える
五・七・五・七・七のリズムは、分かりやすい覚え方の一つです。
何度か口ずさめば、自然と言えるようになってきますよ。
『ハギ キキョウ(五)・クズ フジバカマ(七)・オミナエシ(五)・オバナ ナデシコ(七)・秋の七草(七)』
語呂合わせで覚える
秋の七草は語呂合わせでも覚えやすいです。
五・七・五・七・七のリズムと比較し、頭に入りやすい方で練習してみてくださいね。
『おすきなふくは(お好きな服は)』
お⇒おみなえし(女郎花)
す⇒すすき(ススキ・尾花)
き⇒ききょう(桔梗)
な⇒なでしこ(撫子)
ふ⇒ふじばかま(藤袴)
く⇒くず(葛)
は⇒はぎ(萩)
秋の七草の楽しみ方

秋の七草には、さまざまな楽しみ方があります。
楽しみ方を知っていると、例年とは違った秋を過ごすことができるでしょう。
①鑑賞のタイミング
秋の七草は、種類にもよりますが8月下旬〜10月上旬が見頃です。
散歩やお出かけの際に見つけたら、ゆっくり鑑賞してみてはいかがでしょうか。
②庭や鉢植えで育てる楽しみ
鉢植えや庭で育てれば、自宅で秋の風情を楽しめます。
絶滅危惧の草花でも、園芸用として販売している場合がありますので、探してみてくださいね。
③俳句や短歌など文学に親しむ
万葉集や俳句に登場する花を実際に見ながら読むと、情景がより鮮やかに浮かびます。
興味のある方は、本やネットなどで調べて読んでみてください。
④季節の行事(十五夜など)との組み合わせ
十五夜のお月見にススキを飾るなど、季節行事と組み合わせるとより特別感が出て趣が深まります。
ぜひ今年の十五夜には、楽しみ方の選択肢に入れてみてはいかがでしょうか?
まとめ
秋の七草は、ただの植物の名前ではなく、古くから人々が季節の移ろいを愛でる心の象徴です。
由来や特徴を知っておくと、観光や行事がより豊かになります。
秋の散策の際には、ぜひ探してみてください。
日常の景色もきっといつもと違って見えるはずですよ。